けやきの新緑が鮮やかに映える、赤レンガのキャンパス。金沢美術工芸大学の正面玄関をくぐると、サモトラケのニケ、ラオコーン、ヴェルヴェデーレのアポロンなどの迫力ある石膏像が並ぶ、美術大学ならではの風景に出迎えられる。

特徴的なこのキャンパスも老朽化が進み、2023年、ついに移転を迎える。移転先は、数百メートル先の金沢大学工学部跡地。キャンパス移転に尽力してきたのが、2018年に学長に就任した山崎剛学長だ。
山崎学長は、2005年に日本美術・工芸分野の教員として金沢美大に着任。17年に渡り金沢美大を主観的にも客観的にも見てきた人物のひとりでもある。
山崎学長が移転後のキャンパスに託す思いと、金沢美大という教育機関を通しての「人づくり」について、お話を伺った。
ふたつの意味を持つ「開かれたキャンパス」
現在の金沢美大は、美術という特殊な教育領域も相まって、良い意味でも悪い意味でも閉鎖的な印象を抱かれることの多い学校だ。新キャンパスのコンセプトは「開かれた美の探求と創造のコミュニティ」。明るくオープンなキャンパス像に、期待は高まる。

「教育機関として適切に閉じられ、学生たちが制作に集中できる環境は、何よりも大切な要素です。しかし、自分で作っているだけでは作品としての価値は生まれません。他者の目に触れることで、はじめて作品と呼ばれるようになる。新キャンパスでは、アートプロムナードと遊歩道で敷地から外まで回遊できる導線ができ、導線上にはアートコモンズというギャラリースペースが設けられます」
学生たちが自らの作品を展示するアートコモンズは6ヶ所に設置され、誰でも自由に出入りして展示を見られるようになる。公園の遊歩道を散策する感覚で、学生たちのフレッシュな芸術作品を鑑賞できるのだ。

開かれているのは、学外に向けてのみではない。現在のキャンパスでは専攻ごとに工房が分かれていて、学生は専攻を越えて立ち入る機会は少ない環境だ。ここで、もうひとつの「開かれた」の意味が重要な役割を持つ。
「学生に対しても、開かれたキャンパスになります。どの専攻でも利用可能な共通工房を設けることで、領域を横断した表現の方法を自ら探求できる。いままでは伝統的な美術の領域を設定して、その枠の中での教育が行われていましたが、最近は領域を横断する作風を目指す学生も増えている。グローバルな展開に合わせるように教育内容を拡充し、枠にはまらない制作活動を広げるきっかけになれば」
デジタル化やNFTなど、アートの領域も無限に広がりを見せる昨今、時代の流れを汲んだ改編といえるだろう。
周辺地域だけじゃない、小立野・石引から海外までオープンに
ただ「実はドキドキなんですよ、このエリアへの移転は」と、学長は苦笑いも見せる。小立野の崖上、浮島のような位置から、移転先は住宅地の中。かつては金沢大学工学部だった地ではあるが、当時はグラウンドだった場所に、新たな学び舎は建設中だ。深夜の窓明かりも、制作に没頭する美大ならではの光景ではあったものの、移転先では窓の先に民家がある。工房エリアをロの字に配した「創作の庭」では、防音対策に気を使った設計になっているとはいえ、機械音や石を打つ音は響き渡る。昔はどんちゃん騒ぎで有名だった秋の学祭・美大祭のあり方にも頭を悩ませている。コロナ禍を経てキャンパスライフやお祭り騒ぎのあり方も様変わりしたが、伝統的な風物詩であり学生たちのいちばんの楽しみでもある。何にせよ「常識の範囲内」という言葉に縛られすぎると、学生たちの自由な発想を潰しかねない。

「そういった問題をひとつひとつクリアして、周辺地域のみなさんに受け入れられれば、公園のように行き来できるオープンなエリアになるはずです。そうなることを願いつつ、関わっていくのは直近の地域だけではありません。周辺地域を盛り上げるというよりも、日本中、ひいては世界の人が注目し、ここへ来てくれるという意味での開かれた大学になるといい。それが、結果的に地域周辺エリアを盛り上げることにつながれば、なお良しですね」
同時に、オープンなキャンパスになるいちばんのメリットは「外部の目に触れる機会が増えること」だという。「4年間という短期教育。外から評価される機会を増やし、我々内部の学生や教員が感じる成果が、学外の人から見ても成果となるかどうか、その価値観を共有できるようになるといい」
金沢の街、芸術との距離感
金沢は、伝統工芸が色濃く残る文化都市だ。2004年に金沢21世紀美術館が開館してからは、伝統工芸と現代アートが交差する芸術の街というキャッチコピーも増えてきた。金沢美大着任前、大阪市立博物館学芸員、文化庁文化財調査官を務めた経歴を持つ山崎学長の感じる金沢は、芸術を育む土壌としてどのような印象なのだろうか。
「一般的には、大阪・東京のような大都市のほうが、新しいものを受け入れられやすい印象があるかもしれません。伝統文化が重んじられている金沢には、しがらみが強いんじゃないかと思われがちです。ですが私は、実は逆であるように感じています」
大都市には、作家や職人はもちろん、美術館やギャラリーも圧倒的に多い。しかし多い分、遠い存在になりがちなのだという。「アートワールドのヒエラルキーが源泉としてある。鑑賞する立場としても、それを感じることが多かったです。いっぽうで金沢は、人と芸術との距離感がとても近いように感じます」
たしかに、石川県の伝統工芸は今でも生活の中に息付くものであり、町家や用水などの歴史的景観はいたるところで目にする。買い物ついでに立ち寄れるアートスポットも街中に点在しているし、週末にはどこかしらでアートイベントを楽しめる。
「東京で文化庁の文化財調査官をしていたときには、自分が言うことに対して意見されることがほとんどなかった。でも金沢では、作家さんからしっかり批判されるんです。先生、それは違うよ、と。研究者・作家・批評家が同じ地平に立っていて、声が届く距離にある。逆に、金沢で伝統に縛られていると感じる人たちにとっては、この距離感は近すぎるんじゃないかな。そこを気にせず、お互いに発信できると思える人にとっては、居心地がよいのだと思う」
上下関係や流派などのしがらみは、決して低いハードルではない。しかし、手の届く距離にある。この距離感こそが、金沢の魅力なのだ。
眠る収蔵品に陽の目を、付属美術館の新設
今までのキャンパスには無かった「美術館」の文字も気になるところだ。「実は、美大は良い作品をたくさん持っているんですよ。見てもらわないと、本当にもったいないので」2007年頃、山崎学長(当時は助教授)が担当していた芸術学専攻の授業の一環として、美大の収蔵品を展示した「鴨居玲展」を開催した。「Bar」「廃兵」「酔い候え」などの油画や素描作品を10点ほど展示したところ、話題になり3日間の会期で1,000人ほどの集客があった。美大学内での展示としては、異例のことである。「美大の収蔵庫に鴨居玲作品が10点もあるなんて、誰も知らないんですよね」
価値の高い作品をたくさん所蔵しているにもかかわらず、展示の機会が少なく眠っている状態のものがほとんど。収蔵品リストには、21世紀美術館でおなじみのカプーアや、彫刻家・ロダンなどの作品も名を連ねる。2019年からは学内の展示スペースで定期的に収蔵品展を開催し、認知度も高まり徐々に集客も増えつつある。移転後は、付属美術館という形で収蔵品を展示し、学外の方にも気軽に鑑賞してもらえるようになる。美術ファンとしてはたまらない美術館が、ここにまた増えるのだ。
人生100年時代、生き伸びていける人づくり
美大生は個性的だ、というイメージがある。金沢美大はこれまでも、豊かな発想力で時代を牽引する人材を多く生み出してきた。毎年全国ネットで取り上げられる卒業式に象徴されるように「良い意味で勝手で個性が強い。本当はデリケートなんですけどね」と、学長は優しい眼差しで学生たちを慮る。卒業生に聞くところによると、准教授・教授時代もつねに優しく物腰柔らかく、学生に寄り添ってくれる身近な先生であったという。学長という立場になっても、その人柄は変わらない。
「芸術領域を起点として、長期的に人生を生き伸びていけるタフさを育てることがいちばん大事。能動的に動き、表現して発信して、自分で生きる場所を見つけていけるような力を身につけてほしい」
人生100年時代、終身雇用が崩れていく時代になりつつある中で、磨かれるべき教育がここにある。2023年、開かれた新しいキャンパスで、美術工芸を基盤としながらも枠にはまらない主体的なものづくり、人づくりが始まろうとしている。
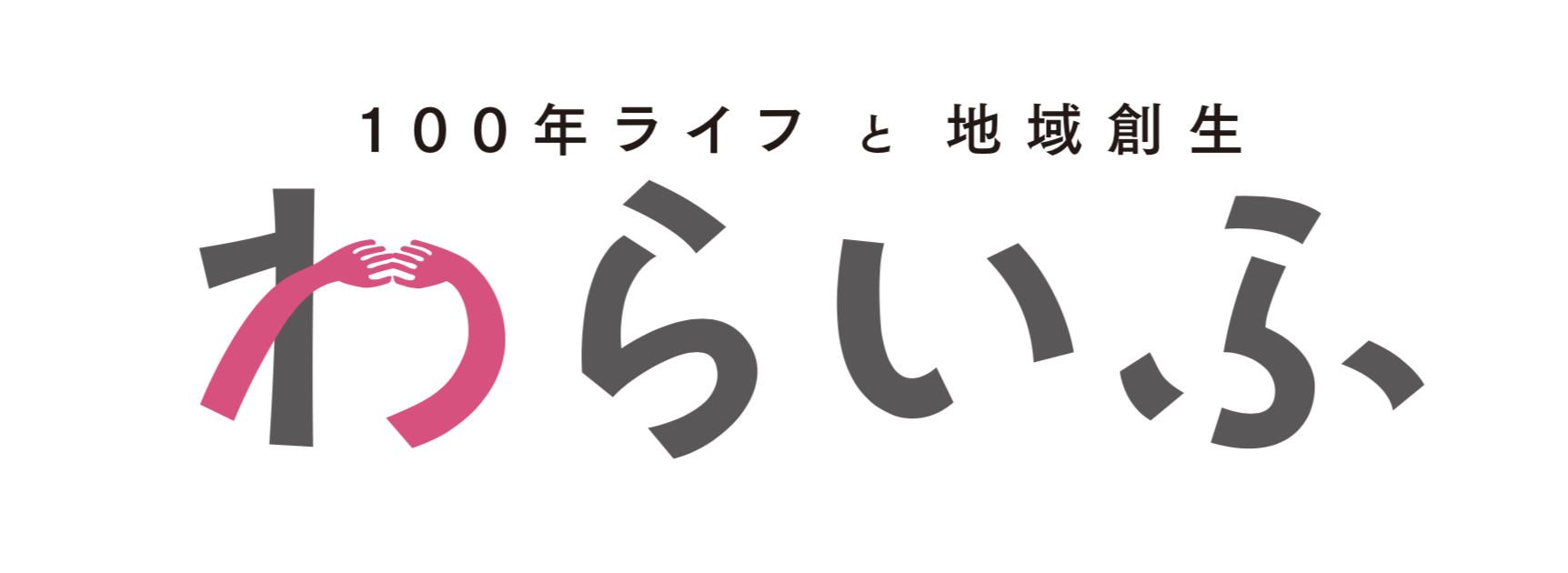



コメント